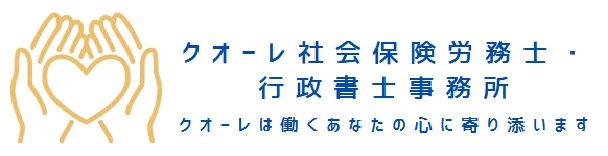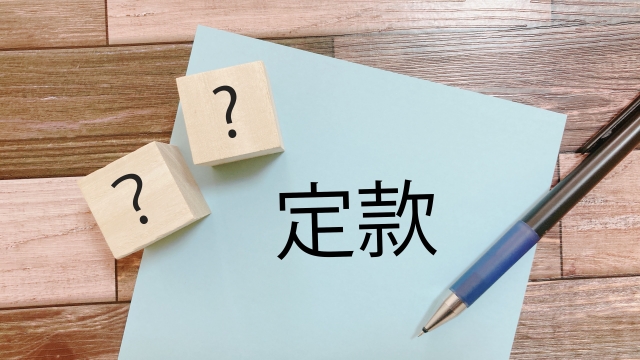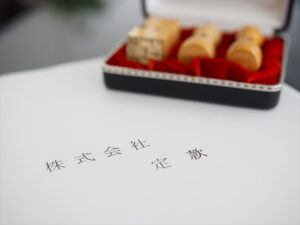株式会社を設立する際に、最も重要な書類のひとつが 「定款(ていかん)」 です。
定款は 会社のルールを定める基本書類 であり、作成時のミスや不備が後々の運営に影響を及ぼすことも…。
今回は、定款作成の基本・注意点・スムーズに作成するコツ をわかりやすく解説します!
1. 定款とは?なぜ重要なのか?
定款とは、会社の基本ルールを定めた書類 で、株式会社設立の際に必ず作成しなければなりません。
定款には 「絶対に記載しなければならない事項」 もあるため、しっかりと作成する必要があります。
定款が必要な理由
- 会社の基本ルールを明確にする(商号・事業目的・役員構成など)
- 法務局での登記に必須(定款がなければ登記できない!)
- 将来のトラブルを防ぐ(会社運営のルールを明確化)
<POINT!>
定款は公証役場で認証を受ける必要がありますが、電子定款なら4万円の印紙代を節約可能!
2. 定款に必ず記載すべき「絶対的記載事項」
定款には、以下の 「絶対的記載事項」 を必ず記載しなければなりません。
絶対的記載事項(記載がないと定款が無効!)
① 商号(会社名) → 「株式会社○○」など、必ず「株式会社」を含める
② 事業目的 → 会社が行う事業内容を具体的に記載
③ 本店所在地 → 会社の本店(住所)を記載(番地まで記載する必要はない)
④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 → 左記に関連して資本金の額、発行する株式の数、発行可能株式数も書くことが多い。
⑤ 発起人の氏名・住所 → 会社を設立する出資者(発起人)の情報
<POINT!>
- 事業目的は 明確に記載すること(抽象的な表現はNG)
- 後から事業目的を追加するには登記の変更が必要 なので、慎重に決める
- 1株の価格をいくらとするかは自由!(1株1万円や5万円をよく見かけます)
3. 記載がしないと効力が生じない「相対的記載事項」
定款には、法律上必須ではないものの、記載しないと効力が生じない項目もあります。
相対的記載事項(記載すると効力が発生する)
代表的なものを下記に記載します
| 項目 | 内容・意義 |
|---|---|
| 変態設立事項(会社法28条) | 現物出資、財産引受、発起人の報酬、 会社が負担する設立費用がある場合、定款に記載が必要。 |
| 設立時取締役及び取締役選任についての累積投票廃除(会社法89条、342条) | 設立時の取締役選任に関し、累積投票(少数株主の影響力を高める制度)を排除する定めができる。 |
| 株主名簿管理人(会社法123条) | 株主名簿の管理を外部の信託銀行等に委託する場合、定款に定めることで可能。 |
| 譲渡制限株式の指定買取人を株主総会や取締役会以外の者とする(会社法140条5項) | 株式譲渡制限会社が指定買取人を別の機関(例:代表取締役)にすることができる。 |
| 相続人等に対する売渡請求(会社法174条) | 相続で取得した株式を会社が買い取れるようにするための規定を定款に設けられる。 |
| 単元株式数(会社法188条1項) | 株式を一定数以上でなければ売買できない「単元株制度」を導入できる。 |
| 株券発行(会社法214条) | 原則として株券は発行しないが、定款で発行する旨を定めることができる。 |
| 株主総会・取締役会・監査役会の招集通知期間短縮(会社法299条1項、368条1項、376条2項、392条1項) | 会社の意思決定を迅速化するため、通知期間を短縮できる。 |
| 取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・委員会の設置(会社法326条2項) | 会社の機関設計を柔軟に決めるため、定款でこれらの設置を定めることが可能。 |
| 取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人の責任免除(会社法426条) | 一定の条件下で、経営者の責任を軽減する規定を定款に盛り込める。 |
| 社外取締役・会計参与・社外監査役・会計監査人の責任限定契約(会社法427条) | 社外役員の責任を一定範囲で制限する契約を定款で許容することができる。 |
| 取締役会設置会社における中間配当の定め(会社法454条5項) | 期の途中で配当を行う「中間配当」のルールを定款で定めることができる。 |
<POINT!>
・ 経営権の安定化 → 譲渡制限株式の指定買取人、相続人への売渡請求、単元株制度
・ 迅速な経営判断 → 取締役会・株主総会の招集通知短縮、中間配当の定め
・ ガバナンス強化・役員のリスク管理 → 責任免除、責任限定契約の定め
・ 機関設計の柔軟性 → 取締役会・監査役会の設置
相対的記載事項は 会社の個別事情に応じて、柔軟なルールを作れる点が特徴 です。
特に 非上場会社やオーナー企業 では、経営の安定化・意思決定の迅速化のために 譲渡制限や役員の責任免除 などを活用することが多いですね。
4. 記載してもOKな「任意的記載事項」
会社の独自ルールを定めるために、自由に記載できる項目もあります。
任意的記載事項(記載しなくてもOK)
代表的なものを下記に記載します
| 分類 | 内容・意義 |
|---|---|
| (1) 株式について | |
| 株主名簿の基準日(会社法124条) | 配当や議決権などの権利確定のため、基準日を設けることができる。 |
| 株主名簿の名義書換手続(会社法133条、134条) | 株式の譲渡や相続に伴う株主名簿の書換手続を定めることができる。 |
| 株券の再発行手続(会社法228条2項) | 紛失・毀損した株券の再発行手続を定款で定めることが可能。 |
| (2) 株主総会について | |
| 定時株主総会の招集時期(会社法296条1項) | 株主総会を毎年いつ開催するかを定款で決めることができる。 |
| 株主総会の議長(会社法315条) | 株主総会の議長を誰が務めるか(代表取締役、会長等)を定めることができる。 |
| 議決権の代理行使(会社法310条) | 株主が代理人を立てて議決権を行使する場合のルールを定款で定めることができる。 |
| (3) 株主総会以外の機関について | |
| 取締役・監査役・執行役の員数 (会社法326条1項、331条4項、402条1項) | 取締役や監査役の最小・最大人数を定款で定めることができる。 |
| 代表取締役・役付取締役(会社法349条3項) | 代表取締役の選定方法や、会長・社長・副社長などの役職を定めることができる。 |
| 取締役会の招集権者(会社法366条1項) | 取締役会を招集できる者(代表取締役、特定の取締役など)を定款で定めることができる。 |
| (4) 計算について | |
| 事業年度 (会社法296条1項、会社計算規則91条2項) | 会社の決算期をいつにするかを定款で定めることができる(例:4月1日~3月31日)。 |
| (5) 公告について | |
| 公告の方法(会社法939条1項) | 会社の公告を ①官報掲載、②日刊新聞紙掲載、③電子公告 のいずれかで行うかを定款で決めることができる。 |
| 公告方法のデフォルト(会社法939条4項) | 定款で定めがない場合、自動的に「官報公告」となる。 |
<POINT!>
・ 株主管理 → 株主名簿の基準日・名義書換手続を明確化
・ 株主総会の運営 → 招集時期・議長・議決権代理行使を定めてスムーズに
・ 経営体制の整備 → 取締役・監査役の員数、役職制度の確立
・ 計算・税務対策 → 事業年度の設定
・ 公告方法の選択 → コスト・透明性のバランスを考慮し決定
特に 公告方法の選択、事業年度の設定、株主総会の円滑な運営 は、実務上の影響が大きいため、慎重に決定することが重要ですね。
5. 定款作成時の注意点
・ 事業目的を慎重に決める!
→ 目的を追加・変更する場合、登記の変更が必要(費用:3万円)
・ 電子定款を活用して4万円を節約!
→ 紙の定款は 印紙代4万円が必要 だが、電子定款なら 無料!
・ 株式の譲渡制限を設定するか検討する!
→ 設定すると 経営権の安定化につながるが、株式譲渡の自由度が下がる
・ 取締役の任期を長めに設定するか決める!
→ 最長10年まで延長可能(変更すると登記手続きが必要)
・ 会社の実態に合った内容にする!
→ 事業内容や経営方針に合わないルールを設定すると、運営に支障が出ることも
6. 定款作成の流れ(簡単ステップ)
ステップ1:会社の基本事項を決定(商号・事業目的・本店所在地など)
ステップ2:定款を作成(記載ミスがないように慎重に!)
ステップ3:公証役場で定款認証(電子定款なら印紙代不要)
ステップ4:法務局に登記申請(定款を添付して申請)
7. 定款作成は専門家に依頼するのがラク!
「事業目的の書き方がわからない…」
「電子定款で4万円節約したい!」
そんな方は、行政書士に依頼するのが断然ラク! 💡
・ 事業内容に合わせた最適な定款を作成!
・ 電子定款対応で4万円節約!
・ 会社設立手続きもまとめてサポート!
株式会社設立サポートなら【クオーレ行政書士事務所】へ!
📞 まずはお気軽にご相談ください! 😊